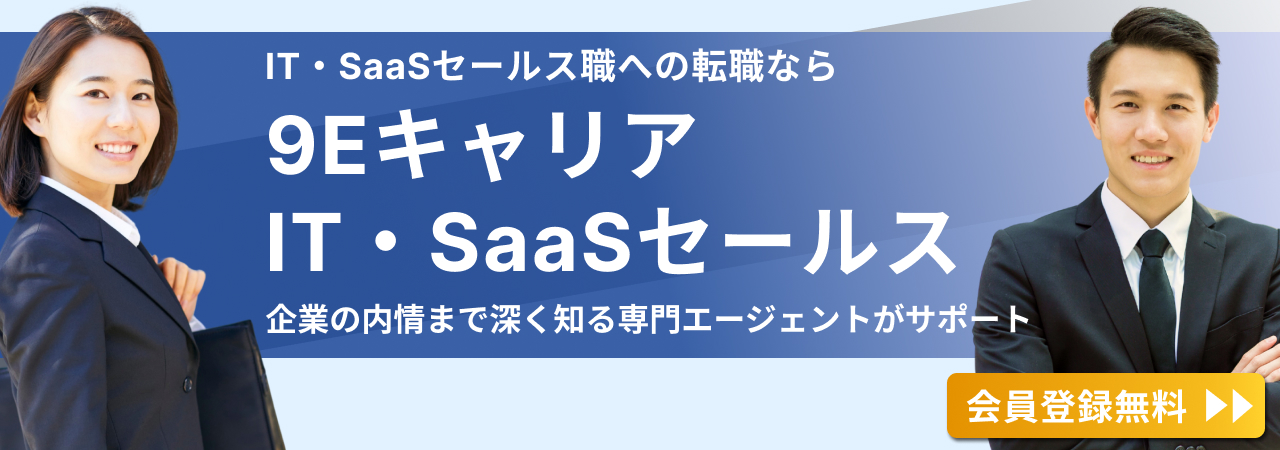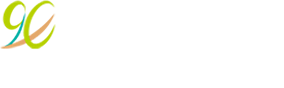2025年7月14日公開
最終更新日:2025年12月24日
SaaS企業の粗利率とは?重要性や計算方法、改善方法を解説
SaaS(Software as a Service)は、従来のソフトウェア販売とは異なり、サブスクリプションモデルにより継続的な収益を生み出す新しい形態です。本記事ではSaaSビジネスにおける「粗利率」に焦点を当て、その定義から計算方法、重要性、改善方法について詳しく解説します。SaaS営業職にとって非常に重要なポイントですので、ぜひお読みください。
【関連記事】当社が運営する「IT・SaaS業界セールス転職支援サービス」の特徴・選ばれる理由・登録のメリットについてご紹介。
SaaSとは何か?
最初に、SaaSとはなにか、SaaSの課金体系であるサブスクリプションモデルと、従来のソフトウェア販売モデルとの違いについて解説します。
SaaSの定義
SaaS(Software as a Service)とは、ソフトウェアをインターネット経由で提供するサービス形態のことです。従来ではユーザーがソフトウェアを買い切りで購入し、ソフトウェアのバージョンアップもユーザー自身が行う必要がありました。
SaaSでは、サービス提供ベンダーがソフトウェアのバージョンアップなどのメンテナンス含め、運用管理を実施します。ユーザーはインターネットに接続できる環境さえあればすぐに利用できるため、導入しやすいというメリットがあります。
SaaSの代表的な例には、オフィスツールとしてGoogle WorkspaceやMicrosoft 365、コミュニケーションツールとしてZoomやSlackなどがあります。
サブスクリプションモデルの特徴
SaaSでは、課金体系としてサブスクリプションモデルが主流です。サブスクリプションモデルは、商品やサービスを使用する権利に対して料金を支払うビジネスモデルです。月額または年額といった決められた期間内でサービスを利用し、その期間ごとに費用を支払います。
サブスクリプションモデルには、企業側とユーザー側の両方に大きなメリットがあります。例えば企業側は、一度ソフトウェアを開発・展開すれば、継続して多数の顧客に提供できるため、安定した収益を得ることができます。一方ユーザー側は、初期費用を抑えつつ、常に最新バージョンのサービスを利用できます。
従来のソフトウェア販売との違い
SaaSを提供する企業にとって、サブスクリプションモデルと従来のソフトウェア販売では営業の仕方が異なります。ソフトウェア販売では、ユーザーがそのソフトウェアを購入することで利益が得られるのに対し、サブスクリプションモデルでは顧客から継続して利用してもらうことで利益を得ます。そのためサブスクリプションモデルでは顧客に継続して利用してもらうために、十分なサービスを提供し続ける事が重要です。
SaaSは安定して利益を得ることができますが、競争が激しく、よいサービスが登場するとすぐに顧客に乗り換えられてしまいます。そのため、サービス提供においては長期的なプランを立て、改善を続け顧客満足度を維持しつづける必要があります。
粗利率とは?
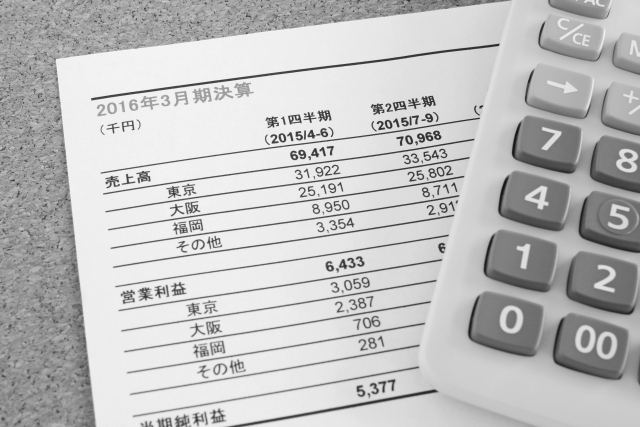
SaaSのように継続的な課金モデルを採用しているビジネスでは、この粗利率を正確に把握し管理することが、持続的な成長を遂げるための重要なポイントです。粗利率が高いということは、それだけ原価を抑えつつ売上を確保できており、将来の販管費や新規投資に資金を回せる余力が大きいことを意味します。逆に粗利率が低い場合は、売上が伸びても原価の負担が重く、経営が不安定になりやすいリスクを孕んでいます。ここでは粗利率およびその目安について解説します。
粗利と粗利率の違い
SaaSビジネスを語る上で欠かせないのが「粗利率」です。粗利率とは、売上高に対してどれだけの「粗利」が得られているかを示す指標です。粗利と粗利率の違いは、以下のとおりです。
粗利(売上総利益):売上高から売上原価を差し引いた金額。実際に残る利益の「総額」
粗利率:粗利を売上高で割った「比率」
粗利率は、企業の収益性を判断する際に、売上に対してどれだけ効率よく利益を上げられているかを示します。企業の成長の度合いを表す指標の1つとして、重要な値です。
SaaS企業における粗利率の目安
SaaS企業における粗利率は、一般的な目安として75%以上が適正とみなされます。業績の良い企業は80%以上を達成する場合もあります。これはソフトウェアを一度開発すれば、新たな顧客に対する追加提供にかかるコストがほとんどないからです。ただし、過度にコストを削るとサービス品質低下や解約率(チャーン)増加を招くため、高い粗利率を維持しつつ顧客満足度を保つバランスが重要です。
SaaSの粗利率はなぜ注目されるのか?

SaaSビジネスにおいて、粗利率はなぜ重要視されるのでしょうか。その理由として2つ挙げられます。
- 継続課金による収益性が高い
- 粗利率が高くなりやすい構造
これらについて詳しく解説します。
継続課金による収益性の高さ
SaaSはサブスクリプションモデルを採用しているため、一度顧客を獲得すると、解約が発生しない限り毎月安定的に売上が発生します。将来の収益予測が立てやすいのが魅力です。また、より品質の高いサービスを提供するアップセルや、追加のサービスやオプションを提供するクロスセルで顧客あたりの単価をさらに引き上げることも可能です。この継続課金による安定した収益構造は、粗利率だけでなく、企業価値を押し上げる重要な要素です。
粗利率が高くなりやすい構造
SaaSで提供するソフトウェアは、一度開発・構築すれば多数の顧客に繰り返し提供しても、発生する追加コストはサーバーリソースやわずかなサポート対応程度で済みます。つまり、売上が増えても原価が比例して増えにくく、結果として粗利率が自然に高い水準になります。さらに、クラウドや自動化ツールの活用によって保守・運用コストを抑えられることも、粗利率を押し上げる要因です。このため、SaaSを資本効率の非常に高いビジネスモデルにしており、多くの企業や投資家が注目する理由です。
SaaSの粗利率の計算方法

粗利率は、SaaSビジネスを運営する上で重要な財務指標の一つです。高い粗利率は投資家からの評価を高め、将来の事業拡大資金を確保するための基盤になります。ここではSaaSにおける粗利率の基本的な計算式、実際の数値例を示しながら具体的に解説します。
計算式の基本
粗利および粗利率は、以下の計算式で算出されます。
粗利=売上高 − 売上原価
粗利率(%)=(売上高 – 売上原価)÷ 売上高 × 100
例えば、月の売上が1,000万円、売上原価が200万円とした場合、
粗利=1,000万円 − 200万円 = 800万円
粗利率=800万円 ÷ 1,000万円 × 100 = 80%
となります。
粗利率80%という数字は、売上のうち80%が利益として残っていることを示します。つまり、20%はコストです。SaaS業界では、この粗利率が70〜90%を超えることも珍しくありません。
このように、粗利率は売上に対してどれだけ利益が残っているかを示す指標です。粗利率が高いほど販管費や営業活動に多く資金を投資でき、より積極的な成長戦略を実現できます。
売上原価に含まれる要素とは?
SaaSビジネスにおける売上原価は、サービスを提供するために必要な費用です。例えば、以下のものが含まれます。
- サーバーやネットワーク、ストレージなどのインフラ費用
- アプリケーションの保守・監視に伴う費用
- カスタマーサポート、カスタマーサクセスの人件費
- 必要なソフトウェアライセンスや外部APIの利用料
実際のSaaSモデルにおける例を紹介
具体的なSaaSモデルを計算例として、見てみましょう。
月額5万円のサービスを100社に提供している場合、月の売上は500万円です。これに対し、
【売上高】
サービス利用料:月額1万円
利用ユーザー:1,000人
売上高:1,000 x 1万円 = 1,000万円
【売上原価】
インフラ費用:30万円
アプリケーション保守・監視費:20万円
カスタマーサポート2名分の人件費:50万円
APIライセンス料:20万円
売上原価:30 + 20 + 50 + 20 = 120万円
粗利=1,000 - 120 = 880 万円
粗利率=(1,000万円−120万円)÷ 1,000万円 ×100 = 88%
このように具体的な数字を出すことで、粗利率をSaaS業界の平均や目標値と比較しやすくなります。
SaaSの原価とは?

粗利率を正確に計算するためには、どのコストを原価に含めるかをきちんと整理しておく必要があります。SaaSビジネスでは目に見える仕入がないため、原価の範囲が曖昧になりがちです。ここではSaaSビジネスにおける原価はどういうものがあるか、解説します。
サーバー費用や人件費の扱い
SaaSビジネスにおいて原価の大部分を占めるのがサーバーやストレージといったインフラ費用です。自社でサーバーやストレージを購入し提供する場合は機器および保守費用、AWSやGCPといったクラウドサービスを利用する場合はその利用料が該当します。また、アプリケーションを運用・監視するためのエンジニアや運用チームの人件費も、コストとして計上します。
これらのコストはユーザーが増えるほど増加する傾向があるため、粗利率の推移を分析する際には慎重な見極めが必要です。
カスタマーサポートや開発コストの位置づけ
顧客からの問い合わせに対応するカスタマーサポートの人件費も、SaaSを利用してもらう上で欠かせません。そのため多くの企業ではサポート費用を売上原価として計上します。一方で開発コストは、既存サービスのバグ修正や軽微な改修は原価に含めるケースが多いですが、新規機能の開発や将来の売上を狙った大規模なR&D(研究開発)は、販管費に計上するケースもあります。
原価と販管費の区別
原価はサービス提供に直接必要なコストを指し、売上が増えるほど比例的に発生します。一方で販管費は、営業・マーケティング活動や管理部門の人件費、オフィス賃料など間接的なコストを指します。粗利率(売上高に対する原価比率)と営業利益率(粗利から販管費を引いたもの)を適切に算出するためには、原価と販管費を明確に区別することが重要です。
販管費と原価の違い

サービス提供に必要なコストである原価に対し、間接的なコストである販管費は、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。SaaS企業における具体的な販管費について解説します。
一般的な販管費の内訳
販管費は主に「販売費」と「一般管理費」に大別されます。具体的には、以下が挙げられます。
【販売費】
- 営業やインサイドセールスの人件費、
- Google広告やSNS広告などのマーケティング費用、
- ウェビナー・展示会など販促活動の費用
【一般管理費】
- 経理・総務・法務・人事といった管理部門の人件費、
- オフィスの賃料や光熱費、
- 会計監査や税理士への報酬
これらはサービス提供自体には直接関与しませんが、事業を運営する上で不可欠なコストです。
原価と販管費の境界線が曖昧なケース
スタートアップなどの小規模な企業では、一人が複数の役割を兼任することが多くなり、原価と販管費の境界が曖昧になりがちです。例えば、カスタマーサクセスが既存顧客への導入支援(原価)だけでなく、関連するサービスの宣伝などマーケティング(販管費)も担当している場合、その人件費をどちらに計上するか判断が難しいケースがあります。また、開発メンバーが既存システムの保守(原価)と新機能開発(販管費や資産計上)を並行して行う場合も同様です。このような場合は、稼働時間や工数比率をもとに按分計算するのが一般的です。
正確な分類が収益性の分析に与える影響
原価と販管費は正確に分類する必要があります。例えば販管費を誤って原価に含めてしまうと、粗利率が不当に低く見え、事業が非効率に見えてしまいます。逆に原価を販管費に入れてしまうと粗利率が過剰に高くなり、経営状態が実態と異なる状態になるリスクもあります。
粗利率が不透明な状態は、投資家や銀行から信頼を失う原因となりかねません。正確な分類は、経営陣が利益構造を正しく理解し、どこにコストを投下すべきかを判断するために重要です。
粗利率を高めるための方法

粗利率を高める方法として、主に3つ挙げられます。
- 自動化や効率化をすすめ、サービス提供コストを下げる
- 顧客単価を向上させLTVを最大化する
- 解約率を下げ、顧客維持率を高める
具体的な方法をそれぞれ解説していきます。
自動化・効率化によるコスト削減
粗利率を上げる方法として最初に紹介するのは、売上原価を減らすことです。SaaSでは主な原価としてインフラ運用やサポート人件費などのコストがあります。このコストを減らす方法として、例えば、CI/CDの導入でデプロイを自動化したり、監視ツールで障害対応を迅速化し、保守エンジニアの負担を軽減したりするなどの方法が有効です。また、チャットボットやナレッジベースを整備してよくある質問を自動対応すれば、サポート対応時間を30%以上削減した事例もあります。
顧客単価の向上とLTVの最大化
粗利率を高めるもう一つの手段は、適切な単価を設定し売上そのものを増やすことです。具体的には顧客単価を引き上げ、顧客が解約するまでに支払われる金額(LTV)を最大化します。料金プランを複数用意し、顧客の成長に合わせてベーシックからスタンダード、プレミアムへ自然に移行してもらう仕組みも有効です。また、API連携やデータ容量増加といったオプション機能を用意し、追加課金で売上を伸ばす方法もあります。さらに年間契約による割引を導入すると月次よりも収益が安定し、顧客の長期化によるLTV向上につながります。
顧客維持率を高める施策
SaaSの粗利率を守る上で顧客維持率を高めることは、極めて重要です。既存顧客を失わないことは新規顧客獲得より3分の1以下のコストで済むと言われています。オンボーディングを丁寧に行うことで解約率(チャーン)低減に直結します。また、定期的なカスタマーサクセス面談で利用状況を把握し、課題を早期に解決することも重要です。さらにツールを使って利用ログをデータ分析し、アクティブ率が低下している顧客には自動リマインドや個別サポートを実施する手法も有効です。
SaaS企業の上場における粗利率の重要性

SaaSビジネスにおける粗利率は、単なる収益性の指標にとどまらず、IPO(株式上場)や大規模な資金調達を目指す際の重要な評価基準です。ここでは、粗利率の重要性について解説します。
投資家が見る指標としての粗利率
投資家は、SaaS企業を評価する際に必ず粗利率をチェックします。なぜなら、粗利率が高ければ高いほど、売上の増加が直接利益や再投資資金として残るためです。粗利率が低いと、成長資金に乏しく、競合とのシェア争いで後れを取るリスクが増大します。投資家はこの数字を見て、ビジネスモデルの健全性と将来性を測っています。
IPO時の評価に与える影響
IPOでは、証券会社や投資家が最も注視する財務指標の一つが粗利率です。SaaSの場合、粗利率75%以上が一つの基準とされ、80%を超えると極めて収益性の高いビジネスと評価されます。粗利率が高いと、それだけ営業や開発に大きく投資をしても将来的にしっかり利益が残ると見なされ、上場時の企業価値も高まりやすくなります。
高粗利率企業の成功事例紹介
世界のSaaS市場には、高い粗利率を維持し、成長を遂げた企業が数多く存在します。代表的な例として、以下の企業があります。
- Salesforce:75.44%
- Dropbox:80.7%
- Zoom:76.59%
また、日本企業では、Sansanやマネーフォワードが70%以上の粗利率を保ちつつ成長し、投資家から高い評価を受けています。
SaaSの原価を理解して粗利率を改善しよう
SaaS業界で営業を行うには、粗利率の計算方法および重要性を正しく理解し、原価と販管費を明確に区分しながら経営全体を常にチェックすることが大切です。また、粗利率を高めるためには、自動化によるサービス提供コストの削減や顧客維持率向上によるコスト最適化に加え、LTVを最大化する、といった戦略を進めましょう。粗利率を単なる会計項目としてではなく、経営戦略の重要な指標として捉えることが、SaaS起業を成功に導く最大のポイントです。本記事で解説した内容をしっかり理解し、SaaS営業に活かしてください。
9EキャリアIT・SaaSセールスの転職支援サービスではIT・SaaS営業職を募集する企業の裏側まで熟知したエージェントが転職を支援いたします。
さらに、応募書類作成のサポートや企業ごとの面接対策など徹底した伴走型の転職支援を提供。「書類も面接もこれまでより通過率がダントツに上がった」「年収交渉をしてもらい希望年収が叶えられた」などクチコミでも高い評価をいただいています。
SaaS営業職への転職をご検討中の方はぜひ以下ボタンより面談予約してください。まだ具体的に転職を考えていない方のご予約も大歓迎です。
この記事の監修者
荒川 翔貴
学生時代に100名規模の営業団体を設立後、大手メーカーで新人賞、売上4,000%増を達成。その後人材業界に転身し、ベンチャー企業にて求職者・企業双方を支援。プレイヤーとして社内売上ギネスを塗り替えながら、3年で事業部長に昇進し組織マネジメントも経験する。
現在は株式会社9Eのキャリアアドバイザーチームリーダーとして、入社半年で再び社内ギネスを更新するなど、常に成果を追求し続けている。(▶︎詳しく見る)
基礎知識のおすすめ記事
-
2025/07/15
SaaSビジネスで受注率を高めるには?基本プロセスからKPI設定、営業戦略の注意点まで解説
-
2025/01/14
The Model型SaaS事業の全体最適化について
-
2025/02/03
【2025年最新】知っておきたいSaaSスタートアップ企業一覧【19社】
-
2025/02/10
【2025年最新】知っておきたいノンデスクワーカー向けSaaS企業一覧【13社】